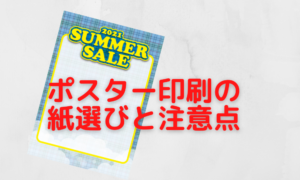チラシやDM、パンフレットなど様々な印刷物が世の中にありますが、一体印刷物を作成するのにかかる費用ってどれぐらいするのでしょうか?
また印刷でかかる費用として最低限必要な項目が幾つかあります。
今回は印刷物をお願いする時にかかる費用や項目についてご紹介していきます。
 プリプロ編集長
プリプロ編集長印刷するのに必要なものと言えば…紙であったり、印刷する版であったり、以外に色々ありますよ。
●印刷物にかかる費用の項目
●費用が高くなるのは?
●印刷費用を賢く抑えるコツ
印刷物にかかる費用の項目
印刷物にかかる費用と一概に言っても、いろいろと種類や項目があります。印刷に詳しくない方でも最低限かかる費用をお分かりであると思いますが、当然ながら『印刷費用・紙』は代表的なものです。その他にも、必ず発生するのが『版』と呼ばれるプレート費用です。印刷する絵柄や内容を反映した刷版とよばれるものです。
①版(プレート)費用
版(プレート)とは一体なんでしょうか?これは刷版と呼ばれるアルミのプレート板のことを言いますが、印刷する絵柄や文字など、内容をこの刷版に焼き付けた上で印刷機に版をセットして印刷します。
この版と呼ばれるものは、カラー印刷の場合はCMYKと呼ばれるプロセスカラーの4版分必要となります。片面で4版ということになりますので、両面カラー印刷の場合は併せて8版の刷版が必要となります。
この1版に※単価〇〇円というように単価がありますので、版費用としては単価×版数でかかる費用が計算できます。
ちなみにA4サイズの両面チラシで言いますと、先程の8版でいけますが、パンフレットなどのページ数が多くなる場合は印刷台数に比例して版数が増えますので、8版が16版や24版と倍々に増えていく事になります。
※単価は印刷会社により設定価格がありますので、実際は発注の際にご確認ください。


②紙 費用
次に必要なものは印刷する紙=印刷用紙にかかる費用となります。
こちらは先程の刷版(プレート)よりかなり複雑で一番費用面で変化がおこるのが印刷用紙となります。
サイズによって価格が変わる
紙の費用を計算するに当たっては、まず使用する紙サイズによっても費用が違います。サイズと一概に言いましてもA4サイズ(210×297㎜)やB5サイズ(182×257㎜)のような、コピーサイズで知られているサイズではありません。印刷用の紙サイズは4/6判、菊全、A判、B判という形で規格サイズが定められており、どのサイズを選ぶかで、紙の費用が変わります。ここでは詳しくは説明はしませんが、印刷物の内容や部数により的確なサイズが選択されます。
厚みや部数により価格が変わる
サイズ以外にも紙には厚みが存在します。折込チラシで使用するかなり薄いペラペラした紙や、カタログで使用する割としっかりした厚み、パッケージやPOPなどで使用する厚紙とよばれるものまで、かなり厚みについてもピンからキリまであります。
よく印刷会社の方から90kgや135kgの厚みですか?っている言葉を耳にされた事はないでしょうか?この90kgや135kgが紙の厚みを指しており、一般的には厚くなる程、紙単価がUPしていきます。
あとは当然ですが印刷する部数が多くなりますと、紙の数量も増加していきますので費用はUPしていきます。紙の数量を表す単位としてR(連数)表示を使います。1Rや5Rという感じで表現します。ちなみに1R=1,000枚を意味しますので、5Rは5,000枚ということになります。
紙の種類により価格が変わる
最後はこちらも当然となりますが、使用する紙の銘柄や種類によって費用が変わります。印刷で非常によく使用される紙質である『コート紙』『マットコート紙』『上質紙』がありますが、こちらも各製紙メーカが製造している銘柄によって費用に違いがあります。
他にも色上質(色のついた上質紙)やキャストコート系(ピカピカ光った光沢紙)やカード紙(厚みがありパッケージやカタログ表紙に使用)他にも特殊紙と呼ばれる、エンボス調や柄が入った紙など、挙げれば無数に印刷用紙はありますので、選択する紙により費用は大きく変わります。
紙の費用についてまとめますと、紙種類を決定すれば、紙単価×厚み×連数で紙の費用が確定します。
実際は紙の連数などは印刷物のサイズにより、丁付けという付け合わせが行われたり、使用する紙サイズにより厚みのところも変化しますので、印刷会社の担当者でなければ理解するには難しくなります。
更に詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。


③印刷費用
次も当然と言えますが…印刷するので印刷工賃はかかります。
印刷費用は一般的には印刷機のサイズによって単価が変わります。チラシやDM向きの小さな印刷機である菊半裁機とパンフレットなどを印刷する菊全機や更にB1ポスターまで印刷できる4/6全般機などがあります。
その機会に応じて通し単価というものが設定されています。通し単価とは1~1,000枚、1,000~2,000枚などのようにおよそどこの印刷会社でも1,000単位で単価設定がされています。大きな印刷用紙が1枚印刷機で印刷されることで、印刷会社はこの1枚を通し枚数と表現し、これにかかる費用を通し単価と呼んでいます。
こちらも1色あたりの単価設定となっていますので、先程の刷版と同様に片面4色カラーの場合は単価〇〇円×4色の費用になります。例えば通し単価1色あたり@5,000円であれば、4色分として片面を印刷するのに20,000円になる計算です。両面カラー印刷の場合は+20,000となり、両面で印刷費は40,000円となります。
④加工の費用
印刷が完了しますと次は加工になります。ここでは加工にかかる費用を説明していきます。
ここでもどのような加工内容を行うかによって当然ですが費用は変わります。
断裁費用
DMやチラシを単純に仕上げる加工となります。印刷物は規格サイズで作成されることが多くA4チラシであれば、規格サイズの210×297㎜のサイズにカットされます。この作業を断裁、または化粧断裁と呼んでいます。刷り上がった印刷物は大きな紙の誌面上に印刷されたままの状態となりますので、実際使用する仕上がりサイズに断裁する必要があります。
折り加工費用
印刷物は仕上げるだけではなく、2つ折りや3つ折りなどの折り加工をする事ができます。この折り加工に関しても断裁費用とは別に加工費用として必要となります。折り加工も様々ありますが、4つ折りやDM折り、観音折りと呼ばれる折り加工がありますが、折り内容が複雑になれば費用も高くなってきます。
また後にご紹介しますが、パンフレットなどは製本加工が必要となります。その製本加工をする前に各ページが本になるように面付された印刷物を折ることになります。ここでも折り加工が発生していきますので、製本費用と併せてかかる費用となります。
折り加工について詳しい内容は下記をご覧ください。


⑤製本費用
パンフレットやカタログなどページ数が8P以上になる印刷物は製本工程が必要となります。先程の折り加工を経て、製本機械にかけてページ順になるように丁合をして最後に表紙を巻いて袋になっている部分を断裁して仕上げます。
この製本も色々種類がありますが、今回は代表的な中綴じ製本と無線綴じ製本を紹介します。
中綴じ製本
中綴じ製本は本のセンターページ(真ん中のページ)をホッチキスで2か所止める製本形式です。最も使用頻度の高い製本方法となりますので、比較的費用も他の製本仕様に比べて安価となります。ただこちらも印刷する紙も厚みにより、折り加工の単位が8Pの場合と16Pの場合で費用が変わりますので、紙が厚くなる場合は製本する数量が増えますので、費用が上がります。
無線綴じ
無線綴じは表紙に背と呼ばれる幅をつくり、本自体がしっかりした印象になります。代表的なものが週刊ジャンプなどが挙げられます。こちらは中綴じとは違い、表紙の背の部分に接着剤である糊を流し込み、中身である本文ページの背の部分をくっつける作業となります。中綴じ製本より手間と工程がかかりますので、費用は高くなります。
その他の製本では上製本(アルバムや記念誌等)に使われる製本方式で、かなり金額がUPします。特別な製本方式となりますので、時間もかかります。
⑥その他の特殊加工
ここまで印刷物を作成する上で一般的に費用がかかる内容をお知らせしてきました。
それ以外にもカタログやパンフレットの表紙に特殊加工をおこなうことで、高級感を演出したり形状を変えたりする加工内容もあります。簡単ではありますが、プラスアルファの特殊な加工内容をご紹介していきます。
ニス加工費
ニス加工(ニス引き)は特殊加工の中でも、かなり安価で表現する事が可能です。ニス加工は印刷での作業となりますので、通常の4色カラー印刷に1色分のニス料金を加える事で反映できます。
ニスはパンフレットの表紙全面に印刷する事も多く、キズや汚れ防止にも役立ちますが、部分的にニスを使用する場合は少し金額的にUPしてしまいます。部分的にニスを使用する場合はニス用の版(プレート)を作成する必要があり、別途版代が必要になりますので、注意が必要です。
PP加工費
PP加工とは(ポリプロピレン素材)のフィルムを使用して熱圧着を加えてパンフレットの表紙-表4に貼り付ける加工となります。雑誌やカタログによく使用される表面加工の1つでありますが、フィルム素材を貼り付けることになりますので、ニス加工より費用は高くなります。
またPP加工には光沢(グロス)とマットのフィルムがあり、マットPP加工の方が一般的に素材の影響もあり費用が高くなります。PP加工をおこなう事で、キズや表面保護の強化に繋がり、高級感がでますので予算に余裕があればオススメです。
箔押し加工費
箔押しとホットスタンプとも呼ばれており、こちらも文字やロゴマークなどを金箔や銀箔を熱で圧着させてキラキラと高級感を持たせる特殊加工となります。パンフレットの表紙タイトルや会社名やロゴなどに使用することが多く、インパクトはありますが、箔押しをする金箔や銀箔の素材費用に加えて、箔押し用の版を作成する費用が別途かかります。
PP加工のように素材をそのまま貼ることでは無く、意図する部分に版を作成して、部分的に加工する内容となりますので素材費用+版費用+箔押し作業費が発生します。また使用する範囲が広範囲であったり、金・銀以外のその他の色箔やパール調の色箔などを選ぶ場合は更に金額がUPしていきます。
トムソン加工費
トムソン抜き加工とは木型と呼ばれる型の原盤を作成し、印刷物の形を丸く抜いたり、モノの形で縁取りしたように抜いたり、または窓のように間を抜いたりする加工内容となります。こちらも、箔押し同様に設計となる木型と呼ばれる刃型を作成し、その型を用いてトムソン機という機械で紙を打ち抜きます。これも型代と抜き加工費用と双方必要になります。
その他にもニスの盛上げ加工やエンボス加工、ラメやホロを用いたPP、匂いがするインクなど様々な印刷加工が沢山あります。先般に紹介した特殊加工より、はるかに素材費用が高くなりますので、特別な印刷媒体を作成する場合にオススメとなります。
費用が高くなるのは?


大まかなではありますが、一般的に印刷物を作成する場合最低限の費用をご紹介してきました。
チラシを印刷する場合とパンフレットを印刷する場合とでは、当然ではありますが、かかる費用は違います。
ここでは費用が上がってしまう、よくある内容をお知らせ致します。
印刷物で費用が上がってしまうよくあるパターン
●特殊な紙を選択した場合
●パンフレットなどで加工内容が多い場合
●チラシやDMなど複数の印刷物を紙を変えたり、厚みを変えたりした場合
特殊な紙を選択した場合
印刷物の費用の中で、紙が占めるウエイトは意外に大きくなります。
その為、紙選びにおいて高価な特殊紙を選択した場合はかなり費用がアップします。ヴァンヌーボやミスターBなどのかなり風合いがあり手触りが良い紙などは1枚単価で購入が必要になるため、紙の費用が大幅にUPします。
一般的なコート紙やマットコート紙などは、ある程度まとまった数量で購入が可能な為、紙の費用が抑えられます。1束(そく)買いと言われますが、250枚や500枚などの単位で購入ができますので、比較的紙費用が安くなります。
予算をかけれる印刷物かどうかを念頭に紙選びは慎重に印刷会社へ相談した方がいいでしょう。
パンフレットなどで加工内容が多い場合
パンフレットを印刷する場合においても、加工内容が多くなると金額がかなりUPしていきます。
PP加工に箔押しなどを双方おこなうことで、パンフレット自身は豪華になりますが、反面金額がかなり上がってしまいます。その上高級な紙を使用している場合はダブルパンチで予算オーバーになってしまいます。どうしても加工内容を充実したい場合は紙を安いものに変更する方が得策と言えるでしょう。
チラシやDMなど複数の印刷物を紙を変えたり、厚みを変えたりした場合
簡単な印刷物であるチラシやDM、ポスターなどは、あまり印刷費用が格段に高くなることはありません。(部数が多いと別ですが…)ただ複数のチラシやDMをまとめてお願いする時に注意が必要となります。
例えば3種類のA4チラシを同時にお願いする時に、それぞれで紙質を変えたり、紙の厚みを変えるとなると逆に高くなります。同じ紙を使用することで部数にもよりますが、印刷では付け合わせ(一緒に印刷できる)が可能となりますので、各々で違いを出したいと思う事もありますが、紙質等を変えることは費用としては逆効果になります。
印刷費用を賢く抑えるコツ
では逆に印刷費を賢く抑えるコツをご紹介していきます。
普段ではあまり意識することもない印刷物の発注ですが、出来る限り予算を抑えたい場合は上手く使えるコツがいくつか存在しますので、活用していきましょう。
印刷物を賢く抑えるコツ
●チラシやDMなどの小さな印刷物は出来るだけ同じタイミングで発注し、紙質も同じにする
●パンフレットはページ数や紙の厚みを調整することで安くなる
●チラシなどで予算が厳しい時にはカラーを2色や1色に変更する
チラシやDMなどの小さな印刷物は出来るだけ同じタイミングで発注し、紙質も同じにする
先程、ご紹介しました費用が高くなる要素でも説明はしてきました。チラシやDMなどを発注する場合、もし2~3種類複数でデザイン違いがあったり、納期が1~2週間あとである場合などいろんなケースがあると思います。
内容確認が取れない場合は仕方ありませんが、もし同時に発注できるのであれば、同じタイミングでお願いする方が効果的です。その場合は同じ紙質で厚みも同じにする方が、印刷時での付け合わせが可能となりますので、非常に安くでお願いできます。
部数が極端に違う場合は付け合わせが出来ない事もありますが、1000部、2000部、1500部などある程度部数が近ければ付け合わせる事は可能となりますので、費用的にはかなりお得となります。
パンフレットはページ数や紙の厚みを調整することで安くなる
次はパンフレットなどページ数がある印刷物を発注する場合に安く工夫できることがあります。
パンフレットのページ数は制作側やクライアント側で調整されるものではありますが、例えばA4サイズのパターンの場合32Pで印刷する場合と28Pで印刷する場合では、どちらが安くなると思いますか?
常識的に考えれば28Pの方がページ数も少なくなりますので、安くなると思いますが、実は32Pの方が安くなる場合が多いのです。使用する紙の厚みにもよりますが、32Pの場合、製本する場合は16P単位で製本する事が可能となりますので、16P(正式には片面8Pの両面で16P)折りが2台で32Pとなりますので、製本費用が抑えられます。
片や28Pの場合は製本する場合、4P+8P+16Pとなりますので、製本する台数が3台となりますので、製本費用が逆に上がります。パンフレットなどの場合は中綴じ製本の場合は通常4P単位でのページ作成になることが殆どです。
製本する上で8P、12P、16P、20P……と4P刻みでページ数の増減ができますので、印刷の面付けなどを印刷会社と相談した上で、安くなるページネーションを組むことも費用を抑えるコツとなります。
また表紙だけ紙を厚くする場合などもよく見られますが、A4サイズの16Pの場合を例に取りますと、表紙台(4P)を135㎏で厚くして、残りの本文12P分を少し薄く110kgでお願いする場合は…逆に高くなります。
もし仮に16Pがすべて110kgの紙でOKの場合は16Pが1台で印刷可能となりますので、版代、印刷費、折り+製本費用が安くなります。これを表紙のみ厚くする事で…表紙4P台と本文12P台を別々で印刷しなければなりません。
この場合は版費用も、印刷費用も同じ紙で16Pの仕様より倍近くの費用がかかります。紙が同じであれば1台で印刷可能となりますが、厚くすることで印刷費等がかなりアップしてしまいます。
仕様に関しては見栄えもあるかと思いますので、中々難しくとは思いますが、少し工夫をしたりすることで金額を抑えることができますので、コツとして利用してみてはいかがでしょうか。
チラシなどで予算が厳しい時にはカラーを2色や1色に変更する
チラシやDMをカラーで印刷する場合、やはり見栄えが良くアピールしやすいので皆さんカラー印刷を選択されます。
ただどうしても予算が厳しい場合があり、でも裏面にも掲載内容を印刷しなければならない場合はどうすればいいのか?
そんな場合は思い切って片面をカラーではなく、2色か1色で印刷すると金額を抑える事が可能です。
カラー印刷はCMYKのプロセスカラーで4色カラーの印刷となりますので、これを2色や1色で印刷する場合は版費用も印刷費用も4色分ではなく2色や1色分の費用となります。1色にすることで、3版、3色分の費用をカットできますので、特色などの色を指定し1色で表現すれば、両面カラー印刷より金額は抑えることが可能です。
まとめ
今回は印刷物を発注する上で、かかる費用を具体的に紹介してきました。
何を作成するかにもよりますが、必ずかかる費用とては、版代(プレート)、印刷用紙代、印刷工賃(刷る費用)加工費(断裁)はどのような印刷媒体でも必要となります。
折り加工や製本などが増えるパンフレットなどは更に費用が上がり、表紙に表面加工をすればプラスアルファで費用がアップしていきます。
出来る限り予算を抑えて印刷物を作成したい企業様が多い中、安く印刷できるネット印刷で発注するのも一つの手段ではありますが、印刷会社へお願いする際もコストダウンを図れる方法がないか、検討してみてはいかがでしょうか。
おさらいで印刷物を安くするコツをもう一度ご紹介してます。
これ以外にも安くなる手法はあるかと思いますので、その時は印刷会社の担当者であれば、色んなパターンや方法を教授してくれると思いますので、迷われた方は相談をしながら、納得のいく印刷物を作成できるようにしていきましょう。
今回は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。